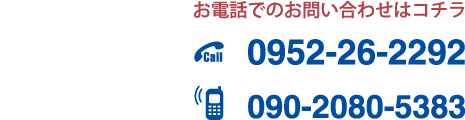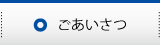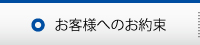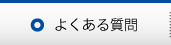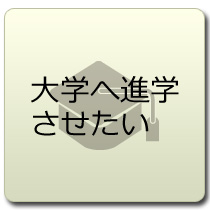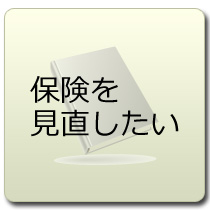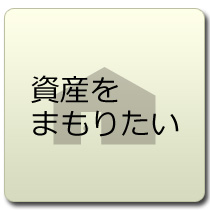お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
生前贈与の基控除額と生命保険のメリットを有効に活用し効率の良い相続を実現させる
プランニングを行います。
.平成27年度からの相続税、贈与税率の改正。教育資金贈与非課税の税制新設の中、
なぜ 「生前贈与」が注目されているのか。
教育資金贈与と生前贈与の主な特徴比較
.生前贈与とは
まず、財産を無償で移転することを「贈与」といいます。
そして、相続人が相続人その他の者に対し、自分の生きているうちに財産を無償で
あげることを「生前贈与」といいます。

生前贈与は贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をして、
相手方がこれを受託することによって成立します。
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに、自分の財産を人に分け与える行為のことを
言います。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
生命保険を使った相続対策で最近注目を集めているのが「保険料贈与プラン」です。
子どもや孫に現金を贈与して、それを保険料として保険に加入する方法です。
この方法なら生命保険で相続財産が増えて、結果、相続税も増えてしまうことを回避できる。
保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠はありますが、それを超えた分は
相続財産に加算され、相続税の対象となります。
相続税の税率は、財産の額が増えるほど税率が上がる仕組みになっており、最高で50%。
15年1月以降は最高55%になります。
せっかく保険金を受け取っても手取り額が減ってしまっては、効果が薄くなってしまいます。
そこで保険料贈与プランを利用する。たとえば、父親が子どもに現金を贈与し、
それを保険料にして保険に加入する。契約者は子ども、被保険者は父親、保険金の受取人は
子どもという形です(図参照)。

この場合、父親に相続が発生したときに子どもが保険金を受け取れるから、相続対策として利用できる。一方で契約者は子どもなので、保険金は相続税の対象ではなく、子ども自身の一時所得として、所得税と住民税の対象となる。
一時所得では、受け取った保険金から支払った保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を差し引いた金額の2分の1が対象となる。
たとえば、総額2500万円の保険料を支払い、5000万円の保険金を受け取ったとすると、
「(5000万円−2500万円−50万円)×2分の1」で1225万円が所得税の対象。
5000万円すべてが課税の対象となる相続税とは大きな違い。
しかし、健康状態によっては父親が加入できない場合もある。が、保険料贈与プランでは、
必ずしも被保険者を父親にする必要はなく、母親や子どもにすることも可能です。
たとえば、贈与を受けた子どもが自分のための個人年金保険に加入する方法もある。
この場合、契約者、被保険者、受取人がすべて子どもになるので、父親の健康状態は
関係ないことになります。
父親が亡くなったときに保険金は受け取れないので、納税資金や遺産争いの防止には
役立たないが、節税効果はあります。
保険料の贈与によって、相続財産を減らすことができるからです。
税務当局に否認されない工夫も
実際にどのくらい贈与したらよいかは、負担率を使うとわかりやすい。
図は相続税と贈与税の負担率を表したものだ。負担率とは、相続財産の額や贈与の額に
対して、支払う税額の比率を示したもの。
たとえば300万円の贈与を行った場合の贈与税の負担率は6.3%。
相続税はどうか。相続人が配偶者と子ども2人で相続財産が2億円の場合、相続税の負担率は
6.8%となります。
相続財産が2億円以上であれば、贈与をしたほうがトクであることがわかります。
このように、贈与税の負担率が相続税の負担率を下回る範囲で贈与を行えば、トータルでの
税負担額を減らすことができます。
ただし、保険料贈与プランを利用する場合には、税務当局に否認されないようにしなければ
ならない。子ども名義で生命保険に加入し、保険料を支払っただけでは、贈与と認められ
ない。
実質的に保険料を支払っていたのは父親であり、贈与はなかったものとみなされてしまう
可能性があるのです。
ではどうすればいいか。国税庁は1983年に事務連絡を行い、以下のような場合には、
「子どもが保険料を負担したと認める」としている。
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)父親が生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できるものがあること
必ずしもすべてを満たす必要はないが、証拠は多いほうがいい。
ひとつでも多くの条件を満たしておいたほうが安心です。
つまり、民法でいう贈与がきちんと行われていることが必要なのです。
目的別・5つの保険料贈与プラン
(1)一次相続対策プラン
保険金を父親の相続税の納税資金として利用するプラン。
子どもが2人以上で分割できる財産がないときには、保険金を相続財産の代わりに分割
(代償分割)することもできる。
●保険の内容
保険種類:終身保険 課税:所得税・住民税(一時所得)
●契約形態
契約者:子ども 被保険者:父親 受取人:子ども
(2)二次相続対策プラン
父親が健康上の理由などで保険に加入できない場合は、母親を被保険者にして
二次相続に備えることができます。
二次相続は一次相続よりも相続税負担が高額になりがちなので効果が高い。
●保険の内容
保険種類:終身保険 課税:所得税・住民税(一時所得)
●契約形態
契約者:子ども 被保険者:母親 受取人:子ども
(3)次世代相続対策プラン
両親がともに保険に加入できない場合に有効なプラン。
贈与で父親の相続財産を減らし、保険金は自分に相続が発生した際に納税資金などに
利用できる。子どもが高齢の場合にも有効。
●保険の内容
保険種類:終身保険 課税:相続税
●契約形態
契約者:子ども 被保険者:子ども 受取人:孫
(4)養老保険プラン
両親ともに保険に加入できない場合で、子どもが満期保険金を教育資金や老後資金に
使いたい場合に有効。
保険期間中に子どもが亡くなった場合には、子どもの相続税の納税資金に使える。
●保険の内容
保険種類:養老保険 課税:満期保険金 所得税・住民税(一時所得)
死亡保険金 相続税
●契約形態
契約者:子ども 被保険者:母親 受取人:子ども
(5)年金プラン
子どもや孫の老後資金として利用するプラン。
資金贈与は子どもや孫の自立を妨げる恐れもあるが、個人年金保険に加入することで、
贈与資金を無駄遣いする心配がなくなる。
●保険の内容
保険種類:個人年金保険 課税:所得税・住民税(雑所得)
●契約形態
契約者:子ども・孫 被保険者:子ども・孫 受取人:子ども・孫
ライフプランからのワンポイントアドバイス
人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。
ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。
世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して
暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに
確認してみてはいかがでしょうか。

あなたはどういう対策を考えますか?
その考えは、ライフプランにあっていますか?
ご相談の方はこちらのホームへ
5年後、10年後、20年後・・・・・
将来の暮らしを思い浮かべてください
それが、あなたと御家族の
ライフプランです。
その夢の実現のために
■今から何をしますか?
■どういった努力をしますか?
・・・・それとも何もしないままですか?
>ご相談の方はこちらのホームへ
お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー
未来あんしい隊
ライフプラン
描けてますか
、
あなたの人生。ご家族の将来。
幸せは、未来を見通すことから。
ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を
シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。
現在と未来。自分と家族。
夢と現実
見えない不安が、確かなあんしんに変わります。
北は北海道から九州までクライアントがいる
プロのファイナンシャルプランナーです。
遠隔地の方もご相談ください。

共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
生前贈与の基控除額と生命保険のメリットを有効に活用し効率の良い相続を実現させる
プランニングを行います。
.平成27年度からの相続税、贈与税率の改正。教育資金贈与非課税の税制新設の中、
なぜ 「生前贈与」が注目されているのか。
教育資金贈与と生前贈与の主な特徴比較
.生前贈与とは
まず、財産を無償で移転することを「贈与」といいます。
そして、相続人が相続人その他の者に対し、自分の生きているうちに財産を無償で
あげることを「生前贈与」といいます。

生前贈与は贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をして、
相手方がこれを受託することによって成立します。
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに、自分の財産を人に分け与える行為のことを
言います。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
生命保険を使った相続対策で最近注目を集めているのが「保険料贈与プラン」です。
子どもや孫に現金を贈与して、それを保険料として保険に加入する方法です。
この方法なら生命保険で相続財産が増えて、結果、相続税も増えてしまうことを回避できる。
保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠はありますが、それを超えた分は
相続財産に加算され、相続税の対象となります。
相続税の税率は、財産の額が増えるほど税率が上がる仕組みになっており、最高で50%。
15年1月以降は最高55%になります。
せっかく保険金を受け取っても手取り額が減ってしまっては、効果が薄くなってしまいます。
そこで保険料贈与プランを利用する。たとえば、父親が子どもに現金を贈与し、
それを保険料にして保険に加入する。契約者は子ども、被保険者は父親、保険金の受取人は
子どもという形です(図参照)。

この場合、父親に相続が発生したときに子どもが保険金を受け取れるから、相続対策として利用できる。一方で契約者は子どもなので、保険金は相続税の対象ではなく、子ども自身の一時所得として、所得税と住民税の対象となる。
一時所得では、受け取った保険金から支払った保険料を差し引き、さらに50万円の特別控除を差し引いた金額の2分の1が対象となる。
たとえば、総額2500万円の保険料を支払い、5000万円の保険金を受け取ったとすると、
「(5000万円−2500万円−50万円)×2分の1」で1225万円が所得税の対象。
5000万円すべてが課税の対象となる相続税とは大きな違い。
しかし、健康状態によっては父親が加入できない場合もある。が、保険料贈与プランでは、
必ずしも被保険者を父親にする必要はなく、母親や子どもにすることも可能です。
たとえば、贈与を受けた子どもが自分のための個人年金保険に加入する方法もある。
この場合、契約者、被保険者、受取人がすべて子どもになるので、父親の健康状態は
関係ないことになります。
父親が亡くなったときに保険金は受け取れないので、納税資金や遺産争いの防止には
役立たないが、節税効果はあります。
保険料の贈与によって、相続財産を減らすことができるからです。
税務当局に否認されない工夫も
実際にどのくらい贈与したらよいかは、負担率を使うとわかりやすい。
図は相続税と贈与税の負担率を表したものだ。負担率とは、相続財産の額や贈与の額に
対して、支払う税額の比率を示したもの。
たとえば300万円の贈与を行った場合の贈与税の負担率は6.3%。
相続税はどうか。相続人が配偶者と子ども2人で相続財産が2億円の場合、相続税の負担率は
6.8%となります。
相続財産が2億円以上であれば、贈与をしたほうがトクであることがわかります。
このように、贈与税の負担率が相続税の負担率を下回る範囲で贈与を行えば、トータルでの
税負担額を減らすことができます。
ただし、保険料贈与プランを利用する場合には、税務当局に否認されないようにしなければ
ならない。子ども名義で生命保険に加入し、保険料を支払っただけでは、贈与と認められ
ない。
実質的に保険料を支払っていたのは父親であり、贈与はなかったものとみなされてしまう
可能性があるのです。
ではどうすればいいか。国税庁は1983年に事務連絡を行い、以下のような場合には、
「子どもが保険料を負担したと認める」としている。
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)父親が生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できるものがあること
必ずしもすべてを満たす必要はないが、証拠は多いほうがいい。
ひとつでも多くの条件を満たしておいたほうが安心です。
つまり、民法でいう贈与がきちんと行われていることが必要なのです。
目的別・5つの保険料贈与プラン
(1)一次相続対策プラン
保険金を父親の相続税の納税資金として利用するプラン。
子どもが2人以上で分割できる財産がないときには、保険金を相続財産の代わりに分割
(代償分割)することもできる。
●保険の内容
保険種類:終身保険 課税:所得税・住民税(一時所得)
●契約形態
契約者:子ども 被保険者:父親 受取人:子ども
(2)二次相続対策プラン
父親が健康上の理由などで保険に加入できない場合は、母親を被保険者にして
二次相続に備えることができます。
二次相続は一次相続よりも相続税負担が高額になりがちなので効果が高い。
●保険の内容
保険種類:終身保険 課税:所得税・住民税(一時所得)
●契約形態
契約者:子ども 被保険者:母親 受取人:子ども
(3)次世代相続対策プラン
両親がともに保険に加入できない場合に有効なプラン。
贈与で父親の相続財産を減らし、保険金は自分に相続が発生した際に納税資金などに
利用できる。子どもが高齢の場合にも有効。
●保険の内容
保険種類:終身保険 課税:相続税
●契約形態
契約者:子ども 被保険者:子ども 受取人:孫
(4)養老保険プラン
両親ともに保険に加入できない場合で、子どもが満期保険金を教育資金や老後資金に
使いたい場合に有効。
保険期間中に子どもが亡くなった場合には、子どもの相続税の納税資金に使える。
●保険の内容
保険種類:養老保険 課税:満期保険金 所得税・住民税(一時所得)
死亡保険金 相続税
●契約形態
契約者:子ども 被保険者:母親 受取人:子ども
(5)年金プラン
子どもや孫の老後資金として利用するプラン。
資金贈与は子どもや孫の自立を妨げる恐れもあるが、個人年金保険に加入することで、
贈与資金を無駄遣いする心配がなくなる。
●保険の内容
保険種類:個人年金保険 課税:所得税・住民税(雑所得)
●契約形態
契約者:子ども・孫 被保険者:子ども・孫 受取人:子ども・孫
ライフプランからのワンポイントアドバイス
人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。
ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。
世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して
暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに
確認してみてはいかがでしょうか。

あなたはどういう対策を考えますか?
その考えは、ライフプランにあっていますか?
ご相談の方はこちらのホームへ
5年後、10年後、20年後・・・・・
将来の暮らしを思い浮かべてください
それが、あなたと御家族の
ライフプランです。
その夢の実現のために
■今から何をしますか?
■どういった努力をしますか?
・・・・それとも何もしないままですか?
>ご相談の方はこちらのホームへ
お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー
未来あんしい隊
ライフプラン
描けてますか
、
あなたの人生。ご家族の将来。
幸せは、未来を見通すことから。
ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を
シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。
現在と未来。自分と家族。
夢と現実
見えない不安が、確かなあんしんに変わります。
北は北海道から九州までクライアントがいる
プロのファイナンシャルプランナーです。
遠隔地の方もご相談ください。