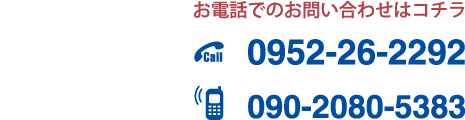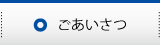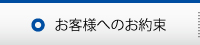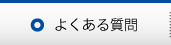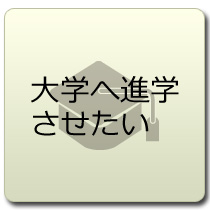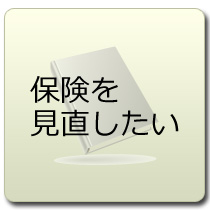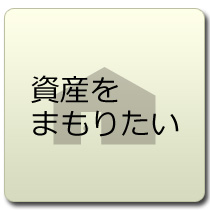お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
「借り換え」というと、より金利の低い変動金利(半年型)や当初固定金利型への借り換えを
イメージするかもしれませんが、今は未曽有の低金利水準時代。
これ以上金利が下がりにくい状況で全期間の返済額を固定できる全期間固定金利型への
借り換えは、今がチャンスといえるかもしれません。

本当に今「借り換え」に有利な時期なのか?
まず、住宅ローンの変動金利(半年型)と全期間固定金利型の金利が何をもとに決められて
いるのかチェックしましょう。わかりやすくまとめると、以下の通りです。
変動金利(半年型)・・・日本銀行の政策金利(0〜0.1%)
全期間固定金利型 ・・・新発10年物国債利回り(3月11日終値 0.41%)
これを見ると、改めて現在の日本の金利が非常に低い状態にあることがわかります。
将来の金利動向を正確に予測することはできませんが、もし下がったとしても余地が限られて
おり、これ以上住宅ローン金利は下がりにくい状況だといえます。
現在、変動金利(半年型)で返済している方の中には、「しばらくは金利が低い状態が続き
そうなのだから、今はこのまま借りておいて、金利が上がってきたら全期間固定金利型に
借り換えをすればいいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、変動金利(半年型)よりも全期間固定金利型のほうが先に金利が上昇することが多い
ですし、金利が急激に上昇した場合には元本の返済がなかなか進まない可能性があります。
金利上昇リスクを回避のためにも、低金利水準の今、できるだけ早いタイミングで全期間固定
金利型の住宅ローンへ借り換えしておくことをおすすめします。
借り換えのメリットを測る判断基準は?
全期間固定金利型への借り換えメリットは、金利上昇リスクヘッジ、家計負担リスクの軽減と
いう観点で考える
一般的によく言われる借り換えメリットが期待できる3条件は、
・金利差1%以上
・住宅ローン残高1,000万円以上
・残りの返済期間10年以上
ですが、必ずしもこの条件を満たしていなくてもメリットがでる可能性があります。
仮に金利差がなくても、借り換えコストが少ないなどのケースによってはメリットが出ること
もあります。
では、変動金利(半年型)から全期間固定金利型へ借り換える場合はどうなるでしょうか?
一般的に、変動金利(半年型)より全期間固定金利型の方が金利が高いので、金利は借り
換え後の方が高くなり、月々の返済額も多くなります。
ただし、全期間固定金利型へ借り換えた場合には、
・将来金利が上昇した場合でも月々の返済額が変わらない
・総返済額が当初からわかるので返済計画を立てやすい
・総返済額が増える心配はなく、繰上返済などで減らす工夫を考えることに意識を向けれ
ばいい
というメリットがあります。
つまり、「現在の月々の返済額が家計上苦しいから借り換える」のではなく、「金利上昇
した場合、家計を圧迫するので今のうちに月々の返済額を固定しておきたい」というケースに
効果的といえます。

変動金利(半年型)から全期間固定金利型へ借り換える際のメリットの見極め方は?
全期間固定金利型へ借り換える場合は、既存の変動金利(半年型)において、
?金利がどの程度まで上昇した場合に借り換えた方が得になるかという「損益分岐の金利」と、
?金利が上昇した場合に「返済額が家計を圧迫しないか?」の、2点を考慮することが大切に
なります。
具体的に、変動金利(半年型)から【フラット35】へ借り換えるケースでみてみましょう。
<当初借り入れ条件> (A銀行 2010年4月に借り入れ)
借入金額 3,000万円 借入期間 35年 元利均等返済 ボーナス返済なし
変動金利(半年型) 金利1.0%
60回返済終了後の住宅ローン残高は、26,329,393円
60回返済終了後、2015年3月末時点での借り換えを検討。
※保証料は別途支払あり。 団信は金利込。
※当初借入時期から金利が変化していないと仮定。

現在借りている金利よりも高い金利への借り換えなので、当然、月々の返済額と年間返済額は
増加します。
ただし、変動金利(半年型)の月々の返済額や残りの総返済額は今後の金利動向によって
変わるので、金利変化も考慮してメリットを見極めることが必要です。
では、変動金利(半年型)について金利水準が上昇した場合に、月々の返済額と残りの総返済
額はどうなるのでしょうか?
<変動金利(半年型)の金利が上昇した場合の月々の返済額と総返済額>
■ケース1:金利が5年ごとに0.5%ずつ上昇したケース

まず、残りの総返済額で比較してみましょう。
仮に、ケース2のように金利水準が5年ごとに0.7%ずつ上昇した場合には【フラット35】への
借り換えが結果的に有利になります。
一方で、月々の返済額で見てみると、ケース1の場合でも、金利が2.0%になった11年目以降、
常に【フラット35】で借り換えた場合の月々の返済額を超えています。
金利水準がいつどのようなペースで上昇するかは誰にもわかりませんが、もし、金利水準が
上昇した時点で、月々の返済額が家計を圧迫するのであれば、金利水準が低い現時点での
全期間固定金利型への借り換えが効果的と考えることができます。
なお、もし当初、民間金融機関で組んだ住宅ローンについて、保証料を別途一括で支払って
いた場合には、見経過分の保証料の一部が返ってくるので、その分を借り換え費用に充てれば
借り換え金額を減らすことも可能です。
もちろん、残りの返済期間やローン残高、手元資金状況などによっては、他の民間金融機関の
より低金利の変動金利(半年型)や当初固定金利型に借り換えた方が、メリットが出る場合も
あるので、借り換えのメリットは、それら複数の選択肢の中から何を一番最優先に考えるのか
で判断しましょう。
実は、以前に借りた【フラット35】から現在の金利水準の低い【フラット35】に借り換え
る場合でも有利?!
もちろん、どの程度の借り換え効果があるかは、ローン残高、残りの返済期間、金利差に
よって変わってきますが、同じ全期間固定金利型同士の借り換えであれば、「金利差による
返済の軽減額」が「借り換えに伴う諸費用」を上回るのであればメリットがでてきます。
具体的な例で見てみましょう。
<2010年4月に【フラット35】で借り入れ(融資率9割以下)、2015年3月末時点で借り換え
を検討した場合>

月々の返済額は12,127円、年間返済額だと145,524円の軽減、総返済額では諸費用込みで考え
て約439万円もの軽減ができ、充分にメリットが得られることがわかります。
残りの返済期間や借り換え先の事務手数料などの条件によっても変わりますが、金利差が
0.5%程度、つまり当初2%程度で【フラット35】を借りた方でもメリットが出てくる可能性が
あるといえます。
ちなみに、2011年以前に借り入れしている場合には、ほぼ金利が2%を超えているので検討の
余地ありですね。
将来的に長期金利が上昇すると、借り換えによる利息軽減効果も薄れてしまいます。
現時点では、もうしばらく長期金利が低い状態が続くと考えられるので、借り換えのチャンス
は続いているといえるでしょう。
無料で借り換え効果がシミュレーションできるサイトもあるので、様々シミュレーションして
みてはいかがでしょうか?
住宅ローン借り換えは家計に合った金額や返済期間で再考を!
住宅の購入から年数が経つに従い、家族構成や夫婦の働き方に変化が生じることもあります。
そうした変化によって住宅ローンを組んだときと家計収支が異なることがあります。
住宅ローンの借り換えは、単に総返済額を抑えるだけでなく、家計に占める大きな支出である
住居費を、現在の暮らしに合わせて見直す好機でもあります。
定年前の住宅ローン完済を目指すなら
30代で住宅ローンを借り入れた場合、住宅ローンの完済が定年後になる人も多いと思います。
定年前の住宅ローンの完済を目指すなら、繰上返済をして返済期間を短縮することももちろん
可能ですが、それだけが手段ではありません。
繰上返済のために用意した資金を活用し、借り換えるのもひとつの手法です。
たとえば、次の住宅ローンを手持ち金を使って借り換えるケースで考えてみます。
<現在の住宅ローン>
住宅ローン残高:2,600万円、残りの返済期間:30年
全期間固定金利型の民間住宅ローン(金利2.41%、毎月返済額は101,518円)
元利均等返済、ボーナス返済なし、団信特約料金利に上乗せ
手持ち金の中から100万円を返済に充て、借入金額を2,500万円にした上で、同じ全期間固定
金利型の【フラット35】(返済期間21年以上、融資比率9割以下)、金利1.46%、
返済期間25年、元利均等返済、ボーナス返済なし、別途団体信用生命保険加入で借り換えた
場合、借り換え後の毎月返済額は99,514円になります。
つまり、毎月返済額は借り換え前よりも低い上に、返済期間を5年短縮することができる
のです(表1参照)。
<表1 借入額を100万円減らして、返済期間を5年短くした場合>

※1 諸費用には印紙税、登録免許税や抵当権設定・抹消にかかる登記費用および事務手数料を
含む。事務手数料は2.16%(消費税込)とする。
※2 表中の団信特約料は総支払額。団信特約料は毎年年払い。
ちなみに、現在の住宅ローンを、借り換えの際に減らした金額と諸費用(初年度団信特約料
89,500円を含む)とほぼ同額の182万円を期間短縮型で繰上返済した場合には、残りの返済期
間は27年1ヶ月となります。
<参考 182万円を繰上返済した試算>
今後の返済期間 27年1ヶ月
今後の返済額 ?32,934,955円
繰上返済額 ?1,820,000円
総支払額 ? + ?34,754,955円
このケースでは、繰上返済するよりも、その資金を使って借り換えを検討した方がより効果が
大きいことがわかります。
教育費がかかる時期の毎月のローン返済額を抑えたいのなら
子どもの成長とともに増えるのが教育費です。中学から私立に通うようになるなど、当初の
想定以上にお金がかかり家計が苦しくなる場合もあります。
毎月の返済額を抑えたい場合、返済期間を延ばして借り換えをするのもひとつの方策です。
借り換えの際に返済期間を延ばすことができる(※注)住宅ローンの一つに【フラット35】
があります。
次の住宅ローンを返済期間を延ばして借り換えるケースで考えてみましょう。
<現在の住宅ローン>
住宅ローン残高:2,000万円、残りの返済期間:18年
全期間固定金利型(30年固定)の民間住宅ローン(金利2.82%、毎月の返済額118,178円)
元利均等返済、ボーナスなし、団信特約料金利に上乗せ
表2は、残高2,000万円の全期間固定金利型の住宅ローンを、借入金額は変えずに、返済期間を
2年延長した上で【フラット35】(返済期間20年以下、融資比率9割以下)、金利1.23%、
返済期間20年、元利均等返済、ボーナス返済なし、別途団体信用生命保険加入で借り換えた
場合のシミュレーション結果です。
毎月の返済額が24,000円ほど下がるだけでなく、総返済額も少なくなり、大学卒業までの
教育費のかかる期間の家計収支にゆとりをもたせることができます。
<表2 借り換え時、借入期間20年にして毎月返済額を軽減した場合>

※1 諸費用には印紙税、登録免許税や抵当権設定・抹消にかかる登記費用および事務手数料を
含む。事務手数料は2.16%(消費税込)とする。
※2 表中の団信特約料は総返済額。団信特約料は毎年年払い。
教育費がかかる前、つまり子どもが中学や高校に入学する前に、借り換えを検討しておくと
良いでしょう。
ただし、表2のように手元資金から諸費用を出す場合、家計に影響が出ないか十分に確認を
行ってください。
諸費用の手出しが難しい場合は、諸費用を借入金額に上乗せして借り換えする方法も
あります。
※注 【フラット35】に借り換える場合、「35年−住宅取得時に借り入れた住宅ローンの
経過期間(1年未満切り上げ)」まで返済期間を延ばすことができます。
住宅ローンの借り換えは、金利だけでなく家計収支の変化に目を向けよう
借り換えをする際には、金利や借り換えにかかる諸費用の比較はもちろん大切です。
しかし、住宅ローンと長く無理なく付き合うためにも、今後の家計収支の変化に目を向けて
早めにアクションを起こすことが大切になってくるでしょう。
借り換えは、自分の家計に合ったものを選び直せる機会ととらえ、前向きに検討してみま
しょう。

共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
「借り換え」というと、より金利の低い変動金利(半年型)や当初固定金利型への借り換えを
イメージするかもしれませんが、今は未曽有の低金利水準時代。
これ以上金利が下がりにくい状況で全期間の返済額を固定できる全期間固定金利型への
借り換えは、今がチャンスといえるかもしれません。

本当に今「借り換え」に有利な時期なのか?
まず、住宅ローンの変動金利(半年型)と全期間固定金利型の金利が何をもとに決められて
いるのかチェックしましょう。わかりやすくまとめると、以下の通りです。
変動金利(半年型)・・・日本銀行の政策金利(0〜0.1%)
全期間固定金利型 ・・・新発10年物国債利回り(3月11日終値 0.41%)
これを見ると、改めて現在の日本の金利が非常に低い状態にあることがわかります。
将来の金利動向を正確に予測することはできませんが、もし下がったとしても余地が限られて
おり、これ以上住宅ローン金利は下がりにくい状況だといえます。
現在、変動金利(半年型)で返済している方の中には、「しばらくは金利が低い状態が続き
そうなのだから、今はこのまま借りておいて、金利が上がってきたら全期間固定金利型に
借り換えをすればいいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、変動金利(半年型)よりも全期間固定金利型のほうが先に金利が上昇することが多い
ですし、金利が急激に上昇した場合には元本の返済がなかなか進まない可能性があります。
金利上昇リスクを回避のためにも、低金利水準の今、できるだけ早いタイミングで全期間固定
金利型の住宅ローンへ借り換えしておくことをおすすめします。
借り換えのメリットを測る判断基準は?
全期間固定金利型への借り換えメリットは、金利上昇リスクヘッジ、家計負担リスクの軽減と
いう観点で考える
一般的によく言われる借り換えメリットが期待できる3条件は、
・金利差1%以上
・住宅ローン残高1,000万円以上
・残りの返済期間10年以上
ですが、必ずしもこの条件を満たしていなくてもメリットがでる可能性があります。
仮に金利差がなくても、借り換えコストが少ないなどのケースによってはメリットが出ること
もあります。
では、変動金利(半年型)から全期間固定金利型へ借り換える場合はどうなるでしょうか?
一般的に、変動金利(半年型)より全期間固定金利型の方が金利が高いので、金利は借り
換え後の方が高くなり、月々の返済額も多くなります。
ただし、全期間固定金利型へ借り換えた場合には、
・将来金利が上昇した場合でも月々の返済額が変わらない
・総返済額が当初からわかるので返済計画を立てやすい
・総返済額が増える心配はなく、繰上返済などで減らす工夫を考えることに意識を向けれ
ばいい
というメリットがあります。
つまり、「現在の月々の返済額が家計上苦しいから借り換える」のではなく、「金利上昇
した場合、家計を圧迫するので今のうちに月々の返済額を固定しておきたい」というケースに
効果的といえます。

変動金利(半年型)から全期間固定金利型へ借り換える際のメリットの見極め方は?
全期間固定金利型へ借り換える場合は、既存の変動金利(半年型)において、
?金利がどの程度まで上昇した場合に借り換えた方が得になるかという「損益分岐の金利」と、
?金利が上昇した場合に「返済額が家計を圧迫しないか?」の、2点を考慮することが大切に
なります。
具体的に、変動金利(半年型)から【フラット35】へ借り換えるケースでみてみましょう。
<当初借り入れ条件> (A銀行 2010年4月に借り入れ)
借入金額 3,000万円 借入期間 35年 元利均等返済 ボーナス返済なし
変動金利(半年型) 金利1.0%
60回返済終了後の住宅ローン残高は、26,329,393円
60回返済終了後、2015年3月末時点での借り換えを検討。
※保証料は別途支払あり。 団信は金利込。
※当初借入時期から金利が変化していないと仮定。

現在借りている金利よりも高い金利への借り換えなので、当然、月々の返済額と年間返済額は
増加します。
ただし、変動金利(半年型)の月々の返済額や残りの総返済額は今後の金利動向によって
変わるので、金利変化も考慮してメリットを見極めることが必要です。
では、変動金利(半年型)について金利水準が上昇した場合に、月々の返済額と残りの総返済
額はどうなるのでしょうか?
<変動金利(半年型)の金利が上昇した場合の月々の返済額と総返済額>
■ケース1:金利が5年ごとに0.5%ずつ上昇したケース

まず、残りの総返済額で比較してみましょう。
仮に、ケース2のように金利水準が5年ごとに0.7%ずつ上昇した場合には【フラット35】への
借り換えが結果的に有利になります。
一方で、月々の返済額で見てみると、ケース1の場合でも、金利が2.0%になった11年目以降、
常に【フラット35】で借り換えた場合の月々の返済額を超えています。
金利水準がいつどのようなペースで上昇するかは誰にもわかりませんが、もし、金利水準が
上昇した時点で、月々の返済額が家計を圧迫するのであれば、金利水準が低い現時点での
全期間固定金利型への借り換えが効果的と考えることができます。
なお、もし当初、民間金融機関で組んだ住宅ローンについて、保証料を別途一括で支払って
いた場合には、見経過分の保証料の一部が返ってくるので、その分を借り換え費用に充てれば
借り換え金額を減らすことも可能です。
もちろん、残りの返済期間やローン残高、手元資金状況などによっては、他の民間金融機関の
より低金利の変動金利(半年型)や当初固定金利型に借り換えた方が、メリットが出る場合も
あるので、借り換えのメリットは、それら複数の選択肢の中から何を一番最優先に考えるのか
で判断しましょう。
実は、以前に借りた【フラット35】から現在の金利水準の低い【フラット35】に借り換え
る場合でも有利?!
もちろん、どの程度の借り換え効果があるかは、ローン残高、残りの返済期間、金利差に
よって変わってきますが、同じ全期間固定金利型同士の借り換えであれば、「金利差による
返済の軽減額」が「借り換えに伴う諸費用」を上回るのであればメリットがでてきます。
具体的な例で見てみましょう。
<2010年4月に【フラット35】で借り入れ(融資率9割以下)、2015年3月末時点で借り換え
を検討した場合>

月々の返済額は12,127円、年間返済額だと145,524円の軽減、総返済額では諸費用込みで考え
て約439万円もの軽減ができ、充分にメリットが得られることがわかります。
残りの返済期間や借り換え先の事務手数料などの条件によっても変わりますが、金利差が
0.5%程度、つまり当初2%程度で【フラット35】を借りた方でもメリットが出てくる可能性が
あるといえます。
ちなみに、2011年以前に借り入れしている場合には、ほぼ金利が2%を超えているので検討の
余地ありですね。
将来的に長期金利が上昇すると、借り換えによる利息軽減効果も薄れてしまいます。
現時点では、もうしばらく長期金利が低い状態が続くと考えられるので、借り換えのチャンス
は続いているといえるでしょう。
無料で借り換え効果がシミュレーションできるサイトもあるので、様々シミュレーションして
みてはいかがでしょうか?
住宅ローン借り換えは家計に合った金額や返済期間で再考を!
住宅の購入から年数が経つに従い、家族構成や夫婦の働き方に変化が生じることもあります。
そうした変化によって住宅ローンを組んだときと家計収支が異なることがあります。
住宅ローンの借り換えは、単に総返済額を抑えるだけでなく、家計に占める大きな支出である
住居費を、現在の暮らしに合わせて見直す好機でもあります。
定年前の住宅ローン完済を目指すなら
30代で住宅ローンを借り入れた場合、住宅ローンの完済が定年後になる人も多いと思います。
定年前の住宅ローンの完済を目指すなら、繰上返済をして返済期間を短縮することももちろん
可能ですが、それだけが手段ではありません。
繰上返済のために用意した資金を活用し、借り換えるのもひとつの手法です。
たとえば、次の住宅ローンを手持ち金を使って借り換えるケースで考えてみます。
<現在の住宅ローン>
住宅ローン残高:2,600万円、残りの返済期間:30年
全期間固定金利型の民間住宅ローン(金利2.41%、毎月返済額は101,518円)
元利均等返済、ボーナス返済なし、団信特約料金利に上乗せ
手持ち金の中から100万円を返済に充て、借入金額を2,500万円にした上で、同じ全期間固定
金利型の【フラット35】(返済期間21年以上、融資比率9割以下)、金利1.46%、
返済期間25年、元利均等返済、ボーナス返済なし、別途団体信用生命保険加入で借り換えた
場合、借り換え後の毎月返済額は99,514円になります。
つまり、毎月返済額は借り換え前よりも低い上に、返済期間を5年短縮することができる
のです(表1参照)。
<表1 借入額を100万円減らして、返済期間を5年短くした場合>

※1 諸費用には印紙税、登録免許税や抵当権設定・抹消にかかる登記費用および事務手数料を
含む。事務手数料は2.16%(消費税込)とする。
※2 表中の団信特約料は総支払額。団信特約料は毎年年払い。
ちなみに、現在の住宅ローンを、借り換えの際に減らした金額と諸費用(初年度団信特約料
89,500円を含む)とほぼ同額の182万円を期間短縮型で繰上返済した場合には、残りの返済期
間は27年1ヶ月となります。
<参考 182万円を繰上返済した試算>
今後の返済期間 27年1ヶ月
今後の返済額 ?32,934,955円
繰上返済額 ?1,820,000円
総支払額 ? + ?34,754,955円
このケースでは、繰上返済するよりも、その資金を使って借り換えを検討した方がより効果が
大きいことがわかります。
教育費がかかる時期の毎月のローン返済額を抑えたいのなら
子どもの成長とともに増えるのが教育費です。中学から私立に通うようになるなど、当初の
想定以上にお金がかかり家計が苦しくなる場合もあります。
毎月の返済額を抑えたい場合、返済期間を延ばして借り換えをするのもひとつの方策です。
借り換えの際に返済期間を延ばすことができる(※注)住宅ローンの一つに【フラット35】
があります。
次の住宅ローンを返済期間を延ばして借り換えるケースで考えてみましょう。
<現在の住宅ローン>
住宅ローン残高:2,000万円、残りの返済期間:18年
全期間固定金利型(30年固定)の民間住宅ローン(金利2.82%、毎月の返済額118,178円)
元利均等返済、ボーナスなし、団信特約料金利に上乗せ
表2は、残高2,000万円の全期間固定金利型の住宅ローンを、借入金額は変えずに、返済期間を
2年延長した上で【フラット35】(返済期間20年以下、融資比率9割以下)、金利1.23%、
返済期間20年、元利均等返済、ボーナス返済なし、別途団体信用生命保険加入で借り換えた
場合のシミュレーション結果です。
毎月の返済額が24,000円ほど下がるだけでなく、総返済額も少なくなり、大学卒業までの
教育費のかかる期間の家計収支にゆとりをもたせることができます。
<表2 借り換え時、借入期間20年にして毎月返済額を軽減した場合>

※1 諸費用には印紙税、登録免許税や抵当権設定・抹消にかかる登記費用および事務手数料を
含む。事務手数料は2.16%(消費税込)とする。
※2 表中の団信特約料は総返済額。団信特約料は毎年年払い。
教育費がかかる前、つまり子どもが中学や高校に入学する前に、借り換えを検討しておくと
良いでしょう。
ただし、表2のように手元資金から諸費用を出す場合、家計に影響が出ないか十分に確認を
行ってください。
諸費用の手出しが難しい場合は、諸費用を借入金額に上乗せして借り換えする方法も
あります。
※注 【フラット35】に借り換える場合、「35年−住宅取得時に借り入れた住宅ローンの
経過期間(1年未満切り上げ)」まで返済期間を延ばすことができます。
住宅ローンの借り換えは、金利だけでなく家計収支の変化に目を向けよう
借り換えをする際には、金利や借り換えにかかる諸費用の比較はもちろん大切です。
しかし、住宅ローンと長く無理なく付き合うためにも、今後の家計収支の変化に目を向けて
早めにアクションを起こすことが大切になってくるでしょう。
借り換えは、自分の家計に合ったものを選び直せる機会ととらえ、前向きに検討してみま
しょう。

ライフプランからのワンポイントアドバイス
人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。
ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。
世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して
暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに
確認してみてはいかがでしょうか。

あなたはどういう対策を考えますか?
その考えは、ライフプランにあっていますか?
5年後、10年後、20年後・・・・・
将来の暮らしを思い浮かべてください
それが、あなたと御家族の
ライフプランです。
その夢の実現のために
■今から何をしますか?
■どういった努力をしますか?
・・・・それとも何もしないままですか?
>ご相談の方はこちらのホームへ お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー
未来あんしい隊
ライフプラン
描けてますか
、
あなたの人生。ご家族の将来。
幸せは、未来を見通すことから。
ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を
シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。
現在と未来。自分と家族。
夢と現実
見えない不安が、確かなあんしんに変わります。
北は北海道から九州までクライアントがいる
プロのファイナンシャルプランナーです。
遠隔地の方もご相談ください。